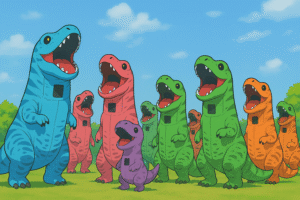石橋屋(懐かしの宮城県)

仙台駄菓子の老舗「石橋屋」は、138年の歴史を持ち、2023年に地震被害で閉店しました。
建物は解体されましたが、敷地内のベニシダレザクラは今も残されています。
駄菓子文化の資料は仙台市歴史民俗資料館に寄贈され、特別展も開催されました。

ねぇ、仙台駄菓子って昔からあるって聞いたけど、「石橋屋」って有名だったの?

はい、「石橋屋」は仙台市若林区舟丁にあった、創業138年の歴史を持つ老舗の仙台駄菓子店でした。創業は1885年(明治18年)で、代々受け継がれながら地元の方々に親しまれてきました。

え、そんなに昔からあったんだ!じゃあ、まだやってるの?

残念ながら、2023年5月に閉店されました。理由は、2022年3月に起きた福島県沖地震で、建物が大きく損傷を受けてしまったからなんです。

地震の影響だったんだ……。お店の建物って、どんな感じだったの?

とても風情のある建物でしたよ。1951年に建てられた木造2階建ての日本家屋で、1994年には「仙台市都市景観賞」を受賞し、2002年には「杜の都景観重要建造物」にも指定されていました。仙台の町並みにとても調和していて、多くの人に愛されていたんです。

へぇ~、じゃあ今はもう建物ないんだね。

はい、今は解体されて更地になっています。ただ、一つだけ残されたものがあります。それが敷地内にあった「ベニシダレザクラ」という桜の木です。樹齢は94年ほどで、毎年春になると見事に咲き誇って、多くの方がその姿を見に訪れていました。

桜は残ってるんだ!なんかホッとするね。で、石橋屋が作ってた駄菓子って、どんなの?

仙台駄菓子の伝統的なものですね。白砂糖や黒糖を使った「うさぎ玉」や「きなこねじり」、米粉を使った「ゆべし」など、素朴でどこか懐かしい味わいが特徴でした。保存料などを一切使わない、体に優しいお菓子でしたよ。

なるほど~。それをもう食べられないのはちょっと寂しいな…。

確かに、製造は終わってしまいましたが、石橋屋が残した文化は形を変えて受け継がれています。例えば、2代目の石橋幸作さんが集めた仙台駄菓子に関する資料や粘土細工など約500点が、仙台市歴史民俗資料館に寄贈されています。

え、それって見られるの?

2024年11月23日から2025年4月13日まで、同資料館で「仙台駄菓子と石橋屋」という特別展が開催されていました。当時の製法や道具、駄菓子を通して地域の文化や暮らしを知ることができる貴重な展示でしたね。

おわっちゃったのか~。駄菓子って懐かしいだけじゃなくて、地域の歴史も詰まってるんだね。

おっしゃる通りです。石橋屋が長年守ってきた駄菓子文化は、仙台の風土や人々の暮らしと深く結びついていて、それ自体が地域の記憶なんです。閉店は惜しまれましたが、その精神は今も静かに息づいています。

うん、なんかちゃんと知れてよかったよ。ありがとう!

どういたしまして。機会があれば、ぜひ桜の季節に跡地にも足を運んでみてください。きっと、石橋屋の面影を感じられると思いますよ。

普通の駄菓子
- 明治時代以降、全国的に広まった安価なお菓子。
- 子ども向けに手軽に楽しめるように工夫されたもの(ガム、ラムネ、チョコ、スナックなど)。
- 工場で大量生産されるものが多く、ポップで派手なパッケージが特徴。
仙台駄菓子
- 江戸時代から伝わる宮城・仙台地方の伝統的な和菓子。
- 米や麦、黒糖、きな粉など自然素材を使い、職人の手作業で作られる素朴な味。
- 「うさぎ玉」「ゆべし」「きなこねじり」など、保存料を使わない体にやさしいお菓子。
そんな仙台駄菓子の歴史あるお店は閉まってしまったけれど、その味はしっかりと残していきたいね。
石橋屋さんのお菓子ではないけれど、仙台駄菓子の楽天市場での購入は↓こちらから
|
|

前の旅は↓ココだよ

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3cf27418.75963897.3cf27419.b572b134/?me_id=1391312&item_id=10000254&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmiyagi-s-iroha%2Fcabinet%2F07645847%2Fimgrc0130875799.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)